
リクルートダイレクトスカウトでは、キャリアの見つめ直しに役立つさまざまなイベントやコンテンツを提供する「働くをひらくDAYS!」を開催。その中、去る11月にサイバーエージェントの財務全般を担当する高本将司氏に、メガバンクからサイバーエージェントに転職した経緯やキャリアの転機、今の仕事のやりがいなどについて語っていただくセミナーを実施しました。今回はそのセミナーの模様を紹介します。
高本将司氏
2013年4月 メガバンクに入行 法人営業としてクライアント対応に従事
2019年1月 株式会社サイバーエージェント入社 財務経理部へジョイン
財務全般(会社のキャッシュ周り)、金融機関対応、中途採用を担当
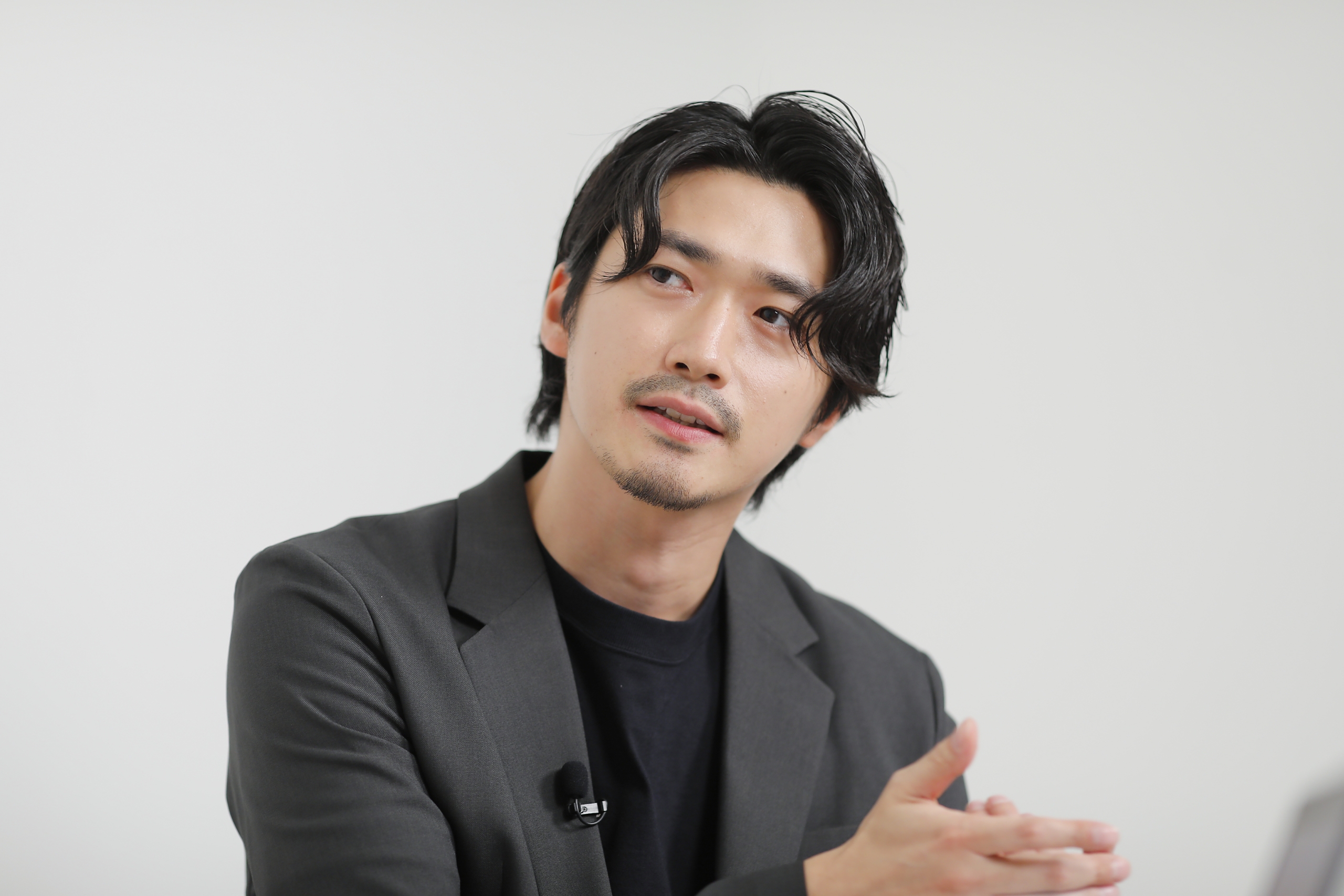
メガバンクの看板を外しても、価値が発揮できる人材になりたい
新卒ではメガバンクに入行しました。法人営業部門に配属となり、数十社のクライアントを担当。企業に対して融資や為替取引、各種法人向けサービスなどさまざまな提案を行いました。既存顧客相手のルート営業もあれば、新規開拓に取り組むこともありました。
新規営業では、いかに相手の懐に入り、信頼関係を構築するかに気を配りました。ただ、なかなか思い通りにならないことが多く、悩むことも多かったですね。最新のニュースを仕入れるなど、顧客との接点になりそうなことから会話の糸口を探って、少しずつ関係性を築いていきました。
メガバンクから転職しようと考えたきっかけは、自身の成長について考えるようになったことでした。銀行のサービスは実はあまり大差がなくて、「メガバンクの看板」を頼りに営業することも多かったです。もちろん、活躍するつもりで入行し意気込んでいたのは間違いないのですが、同年代の友人や、高校・大学時代の同級生がベンチャーで急カーブの成長をしているのを見て、つい自分と比較してしまい、「自分自身が価値のある人間に成長できているのだろうか」と考えるようになりました。
ただ、まだ入行して日が浅かったので、まずは組織やクライアント、市場に対して価値を発揮しなければと考え、結果的に銀行には6年在籍しました。その間、銀行営業には真面目に向き合いましたが、改めて自分は今後何をしたいのか、と頻繁に思うようになり、遂に転職活動を始めました。
サイバーエージェントについては、当時は正直「いろいろな事業を展開している会社」という認識しかなかったのですが、企業研究を進める中で、事業の幅広さだけでなく、企業カルチャーや理念など共感できるものが多く、次第に興味が湧きました。
とはいえ、転職するからには心から納得して決めたいと思い、企業研究はしっかりと行いました。そして当時の銀行の先輩にサイバーエージェントの社員を紹介してもらい、働く中でポジティブな点とネガティブな点両方をヒアリングし、最終的には自分にとって働く魅力のほうが大きいと判断できたことから、転職を決めました。
入社前にしっかりリサーチしていたので、自分の選択に自信をもって入社しましたが、実際ギャップは感じなかったです。
私が転職活動で大事にしていた軸は、全くの異業種(チャレンジ)であること、成長産業であること、そして企業カルチャーが合っていそうかどうかの3つでしたが、この3つ全てを網羅していたのがサイバーエージェントだと感じていました。そして実際に入社した後も、イメージにズレはなかったです。
財務にキャリアチェンジして経営視点で判断することの大切さを学ぶ
入社した直後は最短で成果を上げるために銀行経験を最大に活かそうと考え、金融機関周りの業務や案件は全て私が巻き取ることにしました。例えば、前職では顧客の口座開設を受け付けていましたが、今度は「口座を作る側」に回ることになります。これまでの仕事とはすべて真逆になりますが、勝手は分かっているのでスムーズに業務を巻き取ることができました。
それに付随して、日々の入金管理や債権・債務の管理はもちろん、取引先の審査なども担当しました。サイバーエージェントの特徴の一つに、グループ会社が90社ほどある点が挙げられますが、新たに設立される子会社が多いのも特徴。当時、新たに立ち上がった子会社の経理にアサインしてもらい、そこで経理のイロハも一から学ぶことができました。
バックオフィス部門という性質上、事業に関するクリティカルな問題だけでなく、日常的に各部署から質問や相談が集中します。その際、自分の対応や回答次第で、その後の事業運営、ひいては経営にも影響が出てしまう可能性があります。したがって、いつ何時もブレることなく、一貫したスタンスで対応しなければならないのが、前職の営業時代との大きな違いだと感じました。
日々の細かい業務ももちろん重要なのですが、同時に会社全体を俯瞰して見ながら、経営視点でどのように対応するのが適切なのかを常に考えなければならない点も、前職との大きな違いですね。
ただ、我々バックオフィスから見れば、数ある質問、相談の一つであっても、相手からすれば、重要な案件の一つです。経営視点に立ちながらも、一方で相手とコミュニケーションを取りながら温度感を合わせ、同じ解像度で物事を見て判断するようにしています。
詳細をお伝えするのは難しいのですが、これまで経験した中で特に苦労したのは、営業サイドとして絶対に進めたい大型の案件を取り扱いNGとした時のことでした。大きなPJで、売上のインパクトもあったため、前職での私であれば、「またとない案件だし、業績も拡大するならば通したい」と考えたと思います。
金額だけを見ると良さそうに思えましたが、たとえばクライアントとの契約条件、諸々の付帯条件を勘案すると「“サイバーエージェントとしては”無理に進めないほうが良い」という経営判断になったんです。このようなケースが、これまでに何度かありました。
このような経験を経て、各事業部と同じ目線に立って相談や要望を聞くことはもちろん大切ですが、「常に中立を意識」する重要さに気づきました。経営視点と事業部の視点、双方を理解しながらも、フラットに判断し行動することの重要さを学べたと思います。
初めはその微妙な匙加減がわからず、迷うことも多々ありましたが、その都度周りにフォローしてもらったり、判断を仰いだりすることで乗り越えることが出来ました。また、経営的な決定事項についても、なぜこういう判断に至ったのか自分で仮説を立てて考える習慣をつけるなどして訓練し、自分の軸を固めていきました。

苦労を乗り越えるうえで活きているのは、前職時代に、「想像力を働かせる」ことの重要さを繰り返し教え込まれたことだと思います。新規営業の際は自分の思い通りに話が進むケースは少ないので、相手の気持ちを想像して準備を進めることで、「こういう空気感になったら、このような話に展開していこう」と臨機応変に対応できるよう心がけていました。
その経験を今の役割でも活かし、判断に迷うことがあっても自分なりに想像し、仮説を立てながら進めることができています。
財務中心に、部署横断で難易度の高い案件に取り組む
財務を中心に部署横断で乗り越えた、サイバーエージェントにとって重要な取り組みが「子会社資金の流動化」です。この案件に全社的に取り組めたことが、非常に心に残っています。
「資金の流動化」とは、資金を寝かせない、固定化させないという意味合いがあり、いつでも事業資金として使える状態にしておくことを指します。
たくさんある子会社の中で、ここ数年で急成長している会社があり、その事業内容的に取引規模に見合った資金を内部留保として確保しておく必要がありました。そんな中、万一子会社の資金繰りがうまくいかなくなったり、倒産したりした場合を想定してどう対策を打っておくか、万全なユーザー保護のための姿勢について官公庁からヒアリングが入ったのです。
親会社もいますし、万が一の事態はあり得ないのですが、対応方法について整理し考えておくべきだと捉え、財務を中心に検討に入りました。
一般的には「信託銀行への預託」がセオリーですが、預託はすなわち、資金が固定化されてしまうということ。必要なときに事業資金として活用できないのは、事業の投資効率を著しく悪化させるため、経営判断としてはノーでした。そこで、関係者を巻き込み議論しながら、結果的に直接現金預託をするのではなく「会社の与信を有効活用し」銀行から該当部分の保証を受けるというシンプルなスキームを組成することができました。
このスキーム自体は珍しいものではありませんが、今回の場合は対象債務の限定が非常に難しく、法律に基づく保証ができなかった点がネックでした。そのような中で当社側の顧問弁護士や銀行側の弁護士も含めて何度もディスカッションを重ね、最終的に両者にとって最も良い落としどころを探ることができました。
今回の取り組みで奏功したのは、財務と銀行との関係性ができていたことで物事がスピーディーに進めやすく、意見や提案も聞いてもらいやすい状態にあったのが大きいと思います。
加えて、今回のテーマに関するあらゆる部門と意見をすり合わせながら連携が取れたことも重要だったと思います。契約周りの調整が最も難しかったため、法務とは常に連携を取り、経理や子会社側などバックオフィス部門が一丸となって取り組むことができました。横の連携の強さとスピード感が、サイバーエージェントのバックオフィス部門の強みだと、改めて実感させられました。
サイバーエージェントのバックオフィス部門では、部署ごとに求める経験やスキルは異なりますが、大前提として「素直でいい人」を採用しています。どんな立場の人とも気持ちのいいコミュニケーションができる人、他者からの意見を素直に受け入れられる人であることが必須です。
さらに、変化対応力も必要です。サイバーエージェントは新しいビジネスの芽を見つけて子会社を設立するスピードが速く、組織体制も変わります。常に変化している会社なので、「変化を楽しむ」くらいの姿勢が良いかなと思います。
それに加え、常に自身をアップデートできる人が求められています。事業が変わり、会社が変わり、当社を取り巻く社会もどんどん変化する中で、働く社員自身も変わっていく必要があります。自身に足りないものを見つけ、スキルアップの努力をしてアップデートし続けられる人にジョインしてほしいと願っています。
互いに助け合い協力する文化が根付いている
セミナーに参加している皆さんからいただいた質問について、いくつかお答えします。
Q:私はIT企業で財務として働いていますが、ゴール設定やKPIに悩んでいます。サイバーエージェントの財務のゴールやKPIについて、支障のない範囲で教えてください。
サイバーエージェントでは、一人ひとりのゴールの見極めと目標までの設計を期初の段階でしっかり決めておくことを徹底しています。それにより、期を通してブレずに進むことができるからです。
具体的には、期初に上長や周囲と目線を合わせながら、自身がモチベーションの上がる目標、かつ半期にわたって走り続けられる目標を会話しながら定めます。目標についてGOが出たら、後はゴールに向かってまっすぐ走るのみです。
走りだしの段階でズレのないようにしっかり会話を重ねるのは、サイバーエージェントに根付いている文化でもあります。
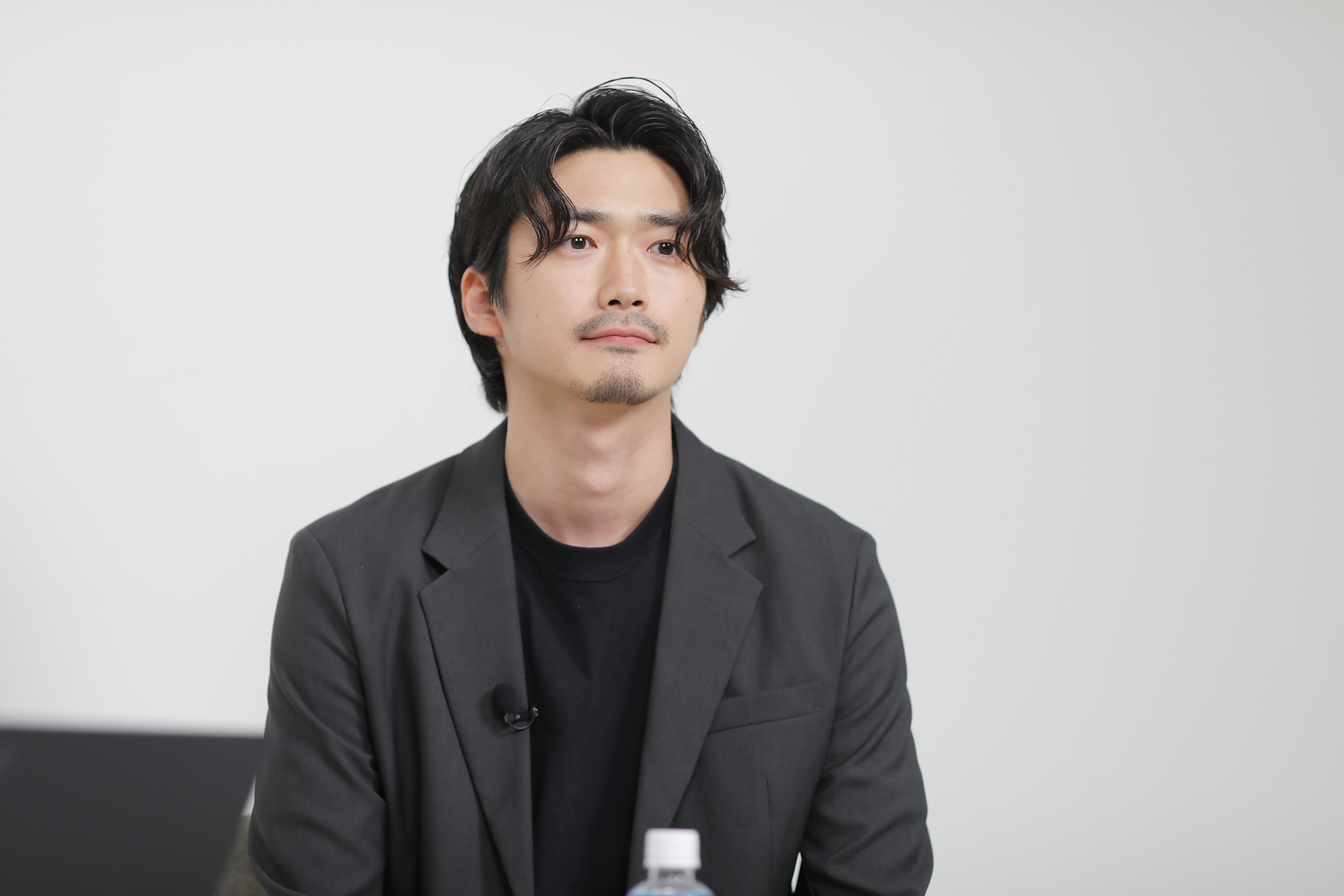
Q:前職の銀行時代は主に財務諸表を見る側で、今は財務諸表を作る側かと思います。似ているようで全く違う部分も多いかと思いますが、このギャップはどのように埋めましたか?
銀行時代から、数字を見る際には想像力を働かせて「企業側でどんな判断が成されて、この数字ができ上ったのだろう?」と考える習慣をつけていたので、志向的にも強み的にも、逆サイドの業務に携れてよかったと思っています。
ただ、確かに会計知識の部分は未経験だったので入社当初は苦労しました。周りにも教えを乞いながら、地道に足りない部分を埋めていった格好です。
サイバーエージェントには、困っている人がいたら組織でフォローし組織で助け合う文化があります。わからないことがあれば、すぐに質問しやすい風土があるので、未経験者でも孤立することはありません。苦労はありましたが、いろいろな人のサポートを得ながら進んでこられたのは、サイバーエージェントだからこそだと思っています。
リクルートダイレクトスカウトでは、さまざまなコンテンツを公開予定
2024年10月より、『リクルートダイレクトスカウト』は、キャリアの新たな選択を後押しするWebサイト「働くをひらくDAYS!」をオープンしました。順次さまざまなテーマのコンテンツを公開します。またリアルでも企業のエグゼクティブやロールモデルとなるトップランナーによるセミナーや、トップキャリアアドバイザーへ直接キャリア相談できる機会などを提供していきます。
「働くをひらくDAYS」のサイトはこちらから↓
https://career.directscout.recruit.co.jp/event
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。




